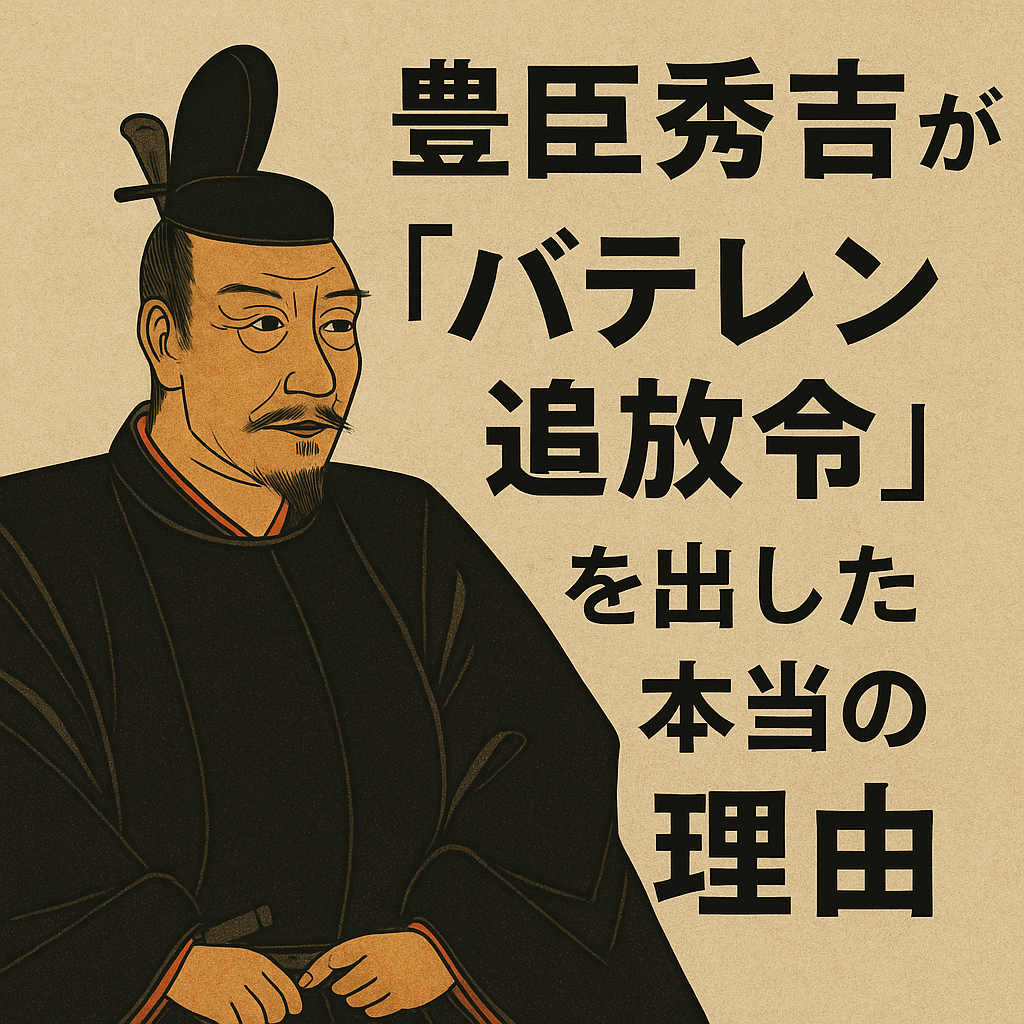
秀吉が「バテレン追放令」を出した本当の理由
信長も秀吉も、最初はキリスト教に寛容だった
戦国時代、日本にはスペインやポルトガルから多くの船が訪れました。
彼らは貿易だけでなく、キリスト教を広めるための宣教師(バテレン)も一緒に送り込んでいました。
実はこの時、日本側も歓迎ムードだったのです。
織田信長はキリスト教を保護し、教会を建てることも認めていました。
豊臣秀吉も当初は似たような立場で、南蛮文化や貿易を通じた交流を重視していたのです。
「まあ、新しい文化も悪くないし、貿易で利益もあるしね。」
そんな空気だったわけです。
ところが1587年、事態は急変する
しかし、ここで大きな転機が訪れます。
1587年、秀吉が九州を平定し、博多に滞在していたときのことです。
仏教の僧たちが秀吉のもとにやってきて、こう訴えました。
「キリスト教徒が神社や寺を壊しています。」
「領民に無理やり入信を迫っています。」
さらに、耳を疑うような話も飛び込んできます。
「日本人が奴隷として海外に売られているんです。」
この時点で、秀吉はかなり不信感を抱き始めました。
貿易だけならまだしも、宗教を利用して人々を支配し、さらに日本人を奴隷にする——。
「これは、ちょっと話が違うぞ。」
そう感じたのは当然でしょう。
高山右近との決断の瞬間
特に象徴的だったのが、キリシタン大名・高山右近とのやりとりです。
秀吉は彼にこう迫りました。
「信仰を捨てるか、日本から出ていくか。」
しかし、右近は信仰を選び、結果として領地を没収され、追放されることになります。
「もうちょっと柔軟に考えてくれても…」
そう思ったかもしれませんが、秀吉の中ではもはや一線を越えていたのです。
さらに決定打となった「サン・フェリペ号事件」
そして極めつけは1596年。
スペイン船「サン・フェリペ号」が土佐沖で座礁し、乗組員がとんでもないことを言い出します。
「まず宣教師を送り、改宗させた後、軍隊で征服する。それが我々のやり方だ。」
この言葉は、秀吉にとって決定打となりました。
「やっぱり、これはただの宗教じゃない。侵略の道具だ。」
ここで秀吉は完全に腹をくくり、キリスト教の取り締まりを一気に強化する方向へ動き出します。
江戸時代へ、そして現代にも通じる話
その後、この方針は江戸幕府にも引き継がれます。
キリスト教は厳しく禁じられ、島原の乱を経て、信仰そのものが徹底的に弾圧される時代へと進んでいきました。
でも、ここで忘れてはならないのは——
「単にキリスト教が嫌いだったわけではない」ということです。
秀吉が見ていたのは、日本という国が侵略されるかもしれないという危機でした。
宗教の背後に潜む、静かなる侵略の可能性。これを食い止めようとしたのです。
現代にも通じる話
今の時代、直接的な軍事侵略は少なくなりました。
でも、経済や文化、価値観を通じた「静かな侵略」は、形を変えて今も存在しています。
「妄信せず注意深く、物事の裏を見ておくべきかもしれない。」
秀吉の決断は、現代を生きる私たちにも、そんな視点を思い出させてくれるのではないでしょうか。
【まとめ】
秀吉のバテレン追放令は、単なる宗教弾圧ではない。
「侵略の芽を摘む」という、安全保障上の決断だったのです。
歴史を知ることで、今の世界をもうちょっと深く考えるヒントが見えてきます。
最近の活動報告
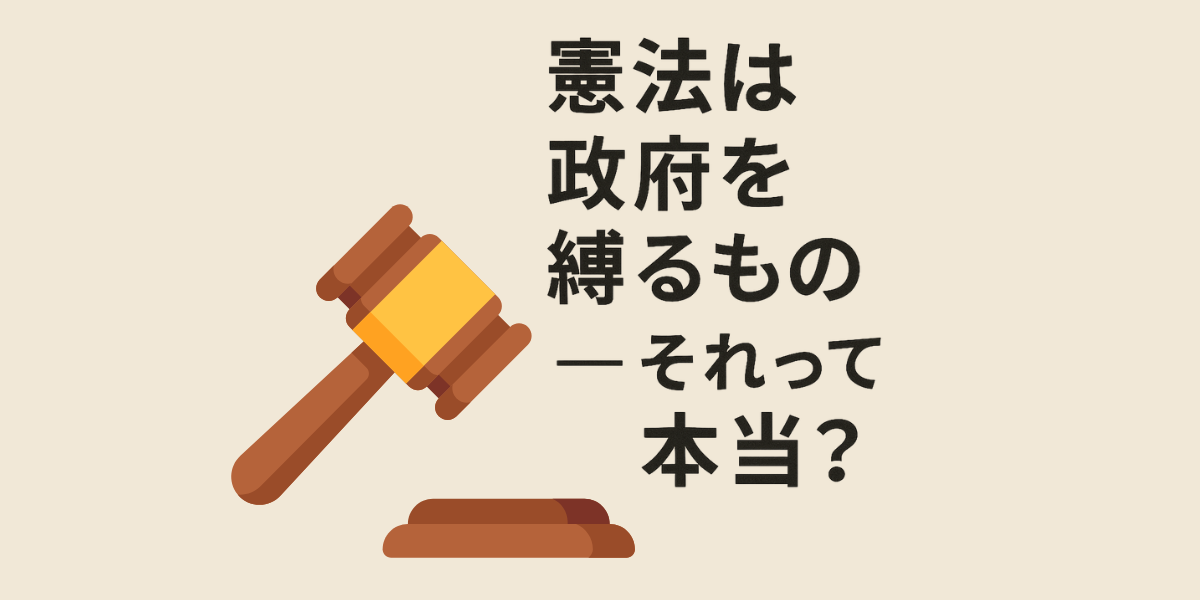
2025/05/21

2025/05/20
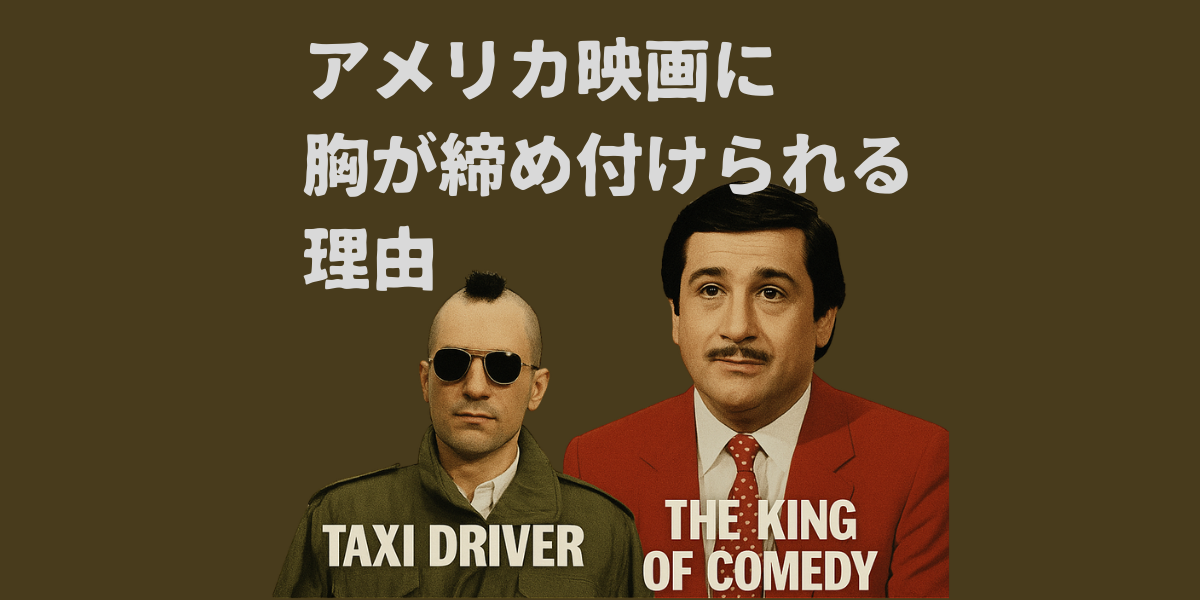
2025/05/20
アーカイブ

