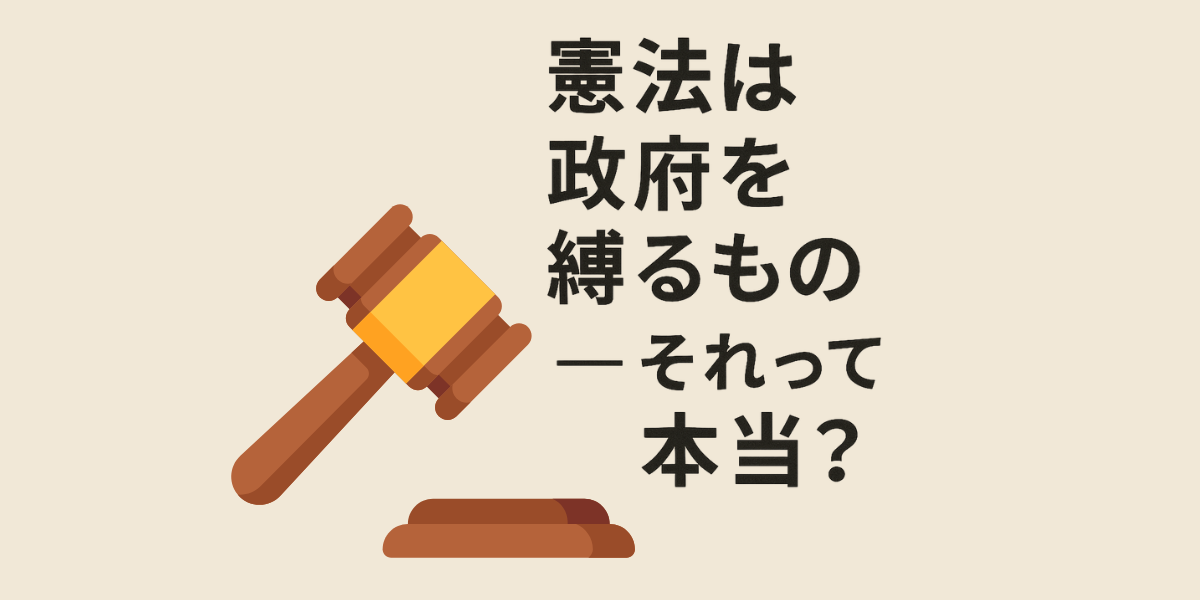
憲法は政府を縛るもの──それって本当?
こんにちは、渋谷区議会議員の矢野けいたです。
最近、「参政党が新しい憲法草案を作ったら、人権の文言が少ないじゃないか」
そんな声が、一部で話題になっています。
「憲法は政府を縛るものだ!人権の欄が減っているのは言語道断だ!」
そんなふうによく言われますが、
私は憲法というものに、少し違った捉え方をしています。
たしかに、今の憲法を開くと「個人の権利」がズラリと並んでいますよね。
だから「憲法=政府を縛るもの」というイメージがあるのも無理はありません。
でもちょっと立ち止まって考えてみてほしいんです。
本当にそうなんでしょうか。
■ 「政府を縛る」の前に、日本の“はじまり”を思い出そう
憲法とは、そもそも“国家のあり方”を定めるものです。
けれど我が国では、そうした「ルール」よりもまず、「こころ」が語られてきました。
たとえば、十七条憲法。
そこには「和をもって貴しとなす」「人の言うことをよく聞け」といった道徳の言葉が並んでいます。
あるいは、明治維新の柱となった五箇条の御誓文。
「広く会議を興し、万機公論に決すべし」──これは、国のトップが国民とともに国を治めていくという宣言でした。
つまり、我が国における“憲法”とはもともと、
誰かを縛る契約書ではなく、みんなで守る誓いのようなものだったのです。
■ 世界のほとんどは「ウシハク国」
古語で「ウシハク」という言葉があります。
これは、“力で治める”という意味です。
世界中のほとんどの国は、そうやって成り立ってきました。
-
王が権力で民を支配し、
-
不満が高まれば革命が起きて、
-
ときにはまったくの外国人が王朝を乗っ取ることもある。
そうして何度も国のかたちが変わってきました。
■ 我が国は「シラス国」
一方、我が国は「シラス国」。
天皇を中心とした精神的な統合のもと、
幕府も政府も、あくまで“天皇の子どもたち”である国民を守るための機構でした。
トップを倒して終わり、という国のつくり方ではなかった。
“家族のようなつながり”が、我が国の根底にはあったのです。
■ だから王朝交代がなかった
世界の国々では、支配者が入れ替わり、
外から来た王朝がそのまま定着することもありました。
でも我が国は違った。
天皇という象徴のもとに、国が守られてきた。
そうして我が国は、世界でも稀なほど、長くひとつの国体を保ってきたのです。
※ちなみに戦後になって使われるようになった「女系天皇」という言葉があります。
これを容認する声もありますが、もし実現すれば、2685年続いた皇統の連続性は断たれ、日本という国の歴史は一区切りを迎えることになります。
■ なのに今、私たちは…
今の憲法は日本人が作ったものではありません。※重要です
戦後、我が国の憲法はGHQによって草案が作られました。
英語を直訳したような条文、急ごしらえの草案――
そこには、我が国の歴史や文化はあまり反映されていませんでした。
にもかかわらず、
「これが唯一絶対の憲法だ」
「政府を縛るための道具なんだから、中身には触れるな」
そんな空気が、いつの間にかできあがってしまった。
■ 無防備すぎる移民政策の裏にも…
こういう“歴史を失った国家観”があるから、
我が国では移民政策や外資への土地売却にも驚くほど無警戒です。
他国には「王朝を乗っ取られた」という記憶があります。
だから、誰が来るのか、何を奪われるのかに敏感です。
でも我が国では、「乗っ取られる」という感覚があまりに希薄。
それが、現在の危うい現実につながっているのではないでしょうか。
■ 参政党の「創憲」とは、過去を捨てることではない
いま私たちが掲げている「創憲」という考え方は、
決して過激な思想でも、懐古主義でもありません。
むしろ、
-
我が国の本来のかたちを思い出し、
-
家族としての国を守り、
-
未来に何を残すかを、自分たちの言葉で決めていく
そんなまっとうな問い直しなのです。
■ 「政府を縛るもの」だけでは足りない
もちろん、権力を抑えるルールは必要です。
でもそれだけで、我が国は守れない。
-
国民がどう生き、
-
どう支え合い、
-
何を大切にしていくか
それこそが、憲法に刻まれるべきではないでしょうか?
■だからこそ護憲でもない改憲でもない…
「創憲」なんです。
我々の手によって憲法を一から作り直すんです。
あなたも同じ一人の日本人として協力してください。
■ あなたなら、何を言葉にしますか?
「憲法なんて、難しそう」
そう思う方も多いかもしれません。
でも、未来の子どもたちに
「これだけは残したい」と思うもの、きっとあるはずです。
それを、私たちの言葉で綴ること。
それが、我が国の憲法を“取り戻す”ということだと、私は思います。
最近の活動報告
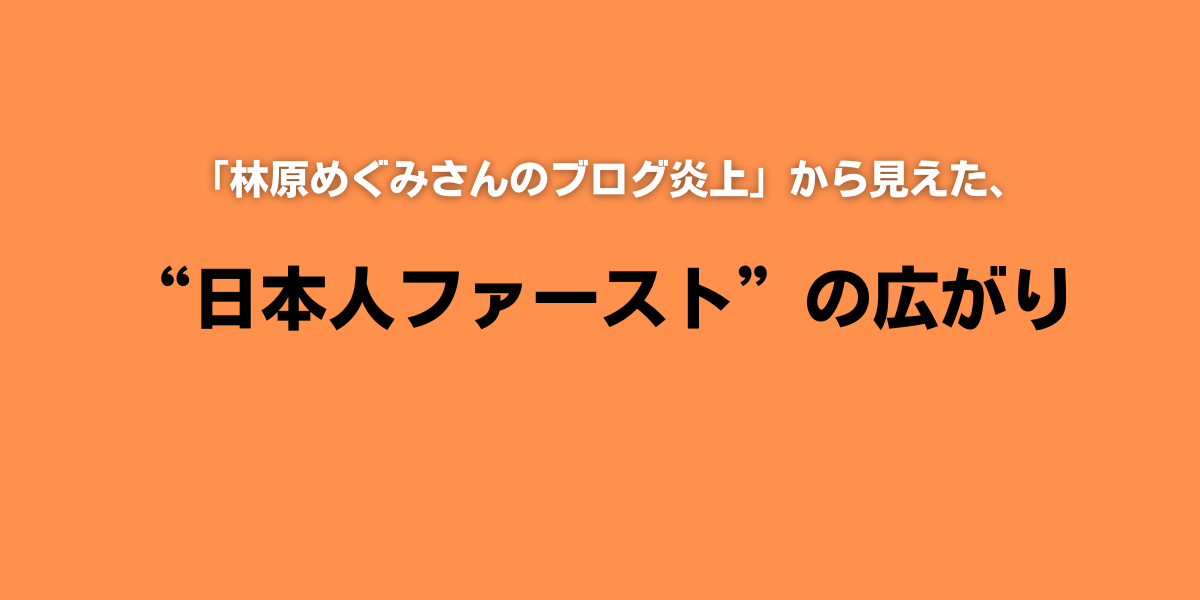
2025/07/23

2025/05/20
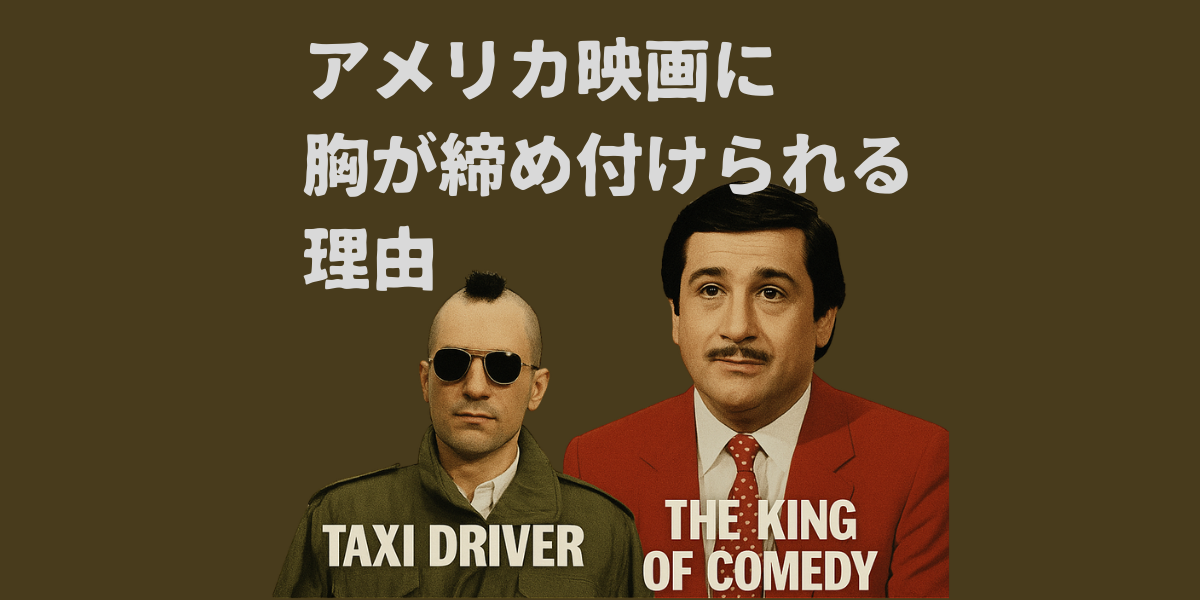
2025/05/20
アーカイブ

